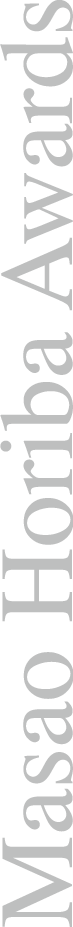| 受賞者名 | 賞 | 所属 | 研究題目 | |
|---|---|---|---|---|
|
2024
堀場雅夫賞
|
2024
堀場雅夫賞
|
国立大学法人東京大学大学院 理学系研究科附属 フォトンサイエンス研究機構
准教授
|
研究題目
超解像赤外顕微鏡および超高速赤外分光法の開発
|
水計測
|
|
水計測
マイクロプラスチック(以下、MPs)※1の化学分析は水環境の保全にとって欠かせない。 赤外分光法※2は有用な化学分析手法の一つであるが、MPsの分析へ適用するにあたって、(1) 1 μm以下の粒子を分析できないこと、(2)分析時間が長いことが欠点として知られていた。 同氏は(1)の課題に対して、中赤外フォトサーマル顕微鏡※3と呼ばれる新たな超解像赤外分光顕微鏡を開発した。 従来法では分析対象の粒子径が数μmに限られていたが、本顕微鏡ではより微細な約100 nmの粒子まで分析可能となった。 これにより、人体からの排出が困難とされる1 μm以下のナノプラスチック※4の計測が可能となった。 (2)の課題に対して、同氏はタイムストレッチ赤外分光法※5と呼ばれる毎秒約1億回の計測が可能な世界最高速の赤外分光手法を開発した。 本手法により短時間での大量の化学分析データ収集手法が開発されたことで、水試料中のMPsの大規模データ解析実現への可能性が示された。1 マイクロプラスチック:環境中に存在する微小なプラスチック粒子。人体・環境への甚大な悪影響が懸念されており、特に海洋環境で懸念材料となっている。2 赤外分光法: 赤外領域の波長の光を試料に照射し、波長ごとの光吸収等を測定する手法。MPsを構成する分子の構造によって光吸収される波長が異なるため、横軸に波長、縦軸に光吸収量あるいは透過光量をプロットした赤外スペクトルを測定することで、MPsにどのような分子が含まれているかを判別できる。3 中赤外フォトサーマル顕微鏡: 試料へ中赤外レーザー光を照射し、中赤外光を吸収する分子近傍の温度上昇 による屈折率変化(フォトサーマル効果)を活用する超解像赤外分光顕微鏡。原理的に中赤外光よりも分析領域が微細な可視光でその屈折率の変化を検出することにより微細な分析領域での赤外分光を実現させている。4 ナノプラスチック: マイクロプラスチックよりもさらに小さく、体内への吸収や環境中での移動が容易で人体や生態系への潜在的な影響が一層懸念されている。5 タイムストレッチ赤外分光法: 様々な波長の光から成る超短パルスレーザー光を試料に照射後、波長ごとの透過光の強度情報(スペクトル)をパルス光強度の時間波形に変換して取得する赤外分光手法。1つの光パルス照射で1回の赤外分光測定が可能となるため、毎秒約1億回光パルスを出力するレーザーと応答速度の速い検出器を用いることで、毎秒約1億回の計測が可能となる。
|
||||
|
2024
堀場雅夫賞
|
2024
堀場雅夫賞
|
中国科学技術大学 環境科学工学部
准教授
|
研究題目
ラボから湖へ:励起発光マトリックスの理論から実践への航海
|
水計測
|
|
水計測
湖沼や河川などの環境水の水質を評価する指標となる水中の溶存有機物の測定において、三次元励起蛍光スペクトル法※1は、測定の迅速さと精度の高さから有効な手段とされている。 しかしながら、この方法を用いて環境水を直接測定する場合には水の濁りが測定結果に影響する事や、取得したデータの処理が煩雑であるなどの課題があった。 Qian氏は、発光ダイオードを励起光源としたポータブルな小型の測定デバイスを開発し、自らが考案したアルゴリズムをデバイスに適用することで、水の濁りの影響を低減し測定精度を高めることに成功し、現場で迅速にかつ正確なデータの取得を実現可能にした。 この研究成果により、三次元励起蛍光スペクトル法を用いた環境水の連続的な水質評価や水処理プロセスのモニタリングへの応用が今後大いに期待される。1 三次元励起蛍光スペクトル法:励起光を試料に照射すると、特定の波長の光を吸収し、吸収した波長より長い波長の光(蛍光)を放出する特性を持つ物質(蛍光性有機物)について、励起波光の波長、放出された蛍光の波長、および蛍光強度を三次元に表したスペクトルデータから分析する手法。
|
||||
|
2024
堀場雅夫賞
|
2024
堀場雅夫賞
|
国立大学法人北海道大学 大学院工学研究院 環境工学部門
准教授
|
研究題目
ウイルス定量法・濃縮法の新規開発に基づいた病原ウイルスの水道原水における存在実態及び浄水処理性の詳細把握
|
水計測
|
|
水計測
病原ウイルスによる水系感染症を制御し、安全な水道水を安定的に供給するためには、病原ウイルスの存在実態、並びに浄水処理工程におけるウイルスの処理状況を把握することが必要不可欠である。 白崎氏は、細菌の生死判別に用いられている光反応性色素とPCR法※1を組み合わせた手法を、ウイルス定量に改良・最適化すると共に、2種類の膜を組み合わせた新たなウイルス濃縮法を開発し、水道原水における病原ウイルスの存在実態の把握と感染力有無の議論を可能とした。 また、開発した濃縮法を実際の浄水場に適用することで、ウイルスの処理状況の評価にも成功した。 更に、培養が困難なノロウイルスのウイルス様粒子※2を作製し、高感度に定量する手法を開発することにより、効率的な培養法の確立を待つことなく、浄水処理工程におけるノロウイルスの除去特性を世界に先駆けて把握することに成功した。 加えて、サポウイルス※3の高濃度精製溶液の調製法及び感染力評価法を確立し、浄水処理工程におけるサポウイルスの除去・不活化特性の把握にも世界で初めて成功した。1 PCR法:ポリメラーゼ連鎖反応(polymerase chain reaction)の略。耐熱性DNAポリメラーゼという酵素の働きにより、DNAサンプルの特定領域を増幅させる手法。2 ウイルス様粒子: 本物のウイルスと粒子径・粒子構造・抗原性が同等な粒子。細胞を用いた培養に頼ることなく、大量に作製が可能。3 サポウイルス: ノロウイルスと同じカリシウイルス科に属するウイルス。ウイルス性胃腸炎の原因となる。
|
||||
|
2024
特別賞
|
2024
特別賞
|
国立研究開発法人 海洋研究開発機構 地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター
研究員
|
研究題目
画像・分光分析技術を応用した、マイクロプラスチック連続モニタリングシステムの開発
|
水計測
|
|
水計測
現在、マイクロプラスチック(以下、MPs)汚染は世界規模で深刻化しており、より詳細な空間・時間スケールでの分布調査が求められている。 しかし、現行の調査では、海表面の情報が主であるうえ、100μm以下の微小なターゲットの情報も少ない。 そこで、高橋氏は非接触・リアルタイムで水中の化合物をそのまま計測できるラマン分光法とホログラフィック画像※1とを統合した新規の連続モニタリング手法を開発した。 この手法によりMPsを含む代表的な海中粒子の分類が可能となり、さらに、水深1000m超で測定可能な自動計測装置の開発・運用を進め、海表面のみならず深海をも含む空間的なMPs・海中粒子の分布情報の取得を目指している。 また、コヒーレント反ストークスラマン散乱法※2を利用して、流動する100μm以下のMPsや藻類を検出・分類できる測定手法も開発した。 この手法により水流中での連続的なモニタリングを実現可能とした。 本研究により、これまでにない詳細なスケールで、空間分布に経時変化を加えたダイナミックなMPs計測を実現でき、海洋汚染の早期コントロールに不可欠な要素技術としての確立が期待できる。1 ホログラフィック画像:光の干渉と回折の現象を利用した画像取得技術。ここでは、散乱光を解析し、大容量空間の任意の位置に存在する物体についてピントの合った画像を再構築する技術として応用。2 コヒーレント反ストークスラマン散乱法: ラマン分光法の一種。2種類の異なる光を物質に照射して生じる振動数差と試料分子の振動数を一致させ入射光と相互作用させることで、微弱なラマン信号を強制的に発生させることができる。
|
||||
|
2024
特別賞
|
2024
特別賞
|
ウォーリック大学 化学科
助教授
|
研究題目
水環境や他の領域において主要分析対象を検出するためのホウ素ドープダイヤモンド電極の開発
|
水計測
|
|
水計測
環境水・飲料水の水質計測において溶存酸素、pHおよび重金属は重要な環境指標であり、その迅速でかつ正確な測定は欠かすことはできない。 しかし、従来のセンサーでは測定に要する時間や耐久性に課題があった。 そこでリード氏は、ホウ素ドープダイヤモンド(以降、BDD)※1電極を用いて溶存酸素濃度と pH を同時に測定可能なセンサーと、電極の局所的なpHを 制御しつつ重金属を測定可能なセンサーを開発した。 BDD 電極表面に部分的に特殊なレーザー加工を施すことで、溶存酸素濃度とpH を同時にかつ短時間に測定することができる堅牢なセンサーの開発に成功した。 さらにディスク型BDD電極の周囲にリング型BDD電極を配置したリングディスク電極を開発することで、リング電極表面における水の電気分解により発生する水素イオンの流束によって、ディスク電極の局所的なpH を定量的に制御しつつ、重金属を測定することに成功した。 これにより、従来のセンサーでは必要とされた試料の前処理が不要となり、迅速でかつ正確なリアルタイムモニタリングを実現可能にした。 これら技術は、単に環境分野だけでなく医療分野など幅広い分野の分析にも貢献することができる。1 ホウ素ドープダイヤモンド(BDD):ホウ素をドーピングしたダイヤモンドであり、金属様導電性を示す。物理・化学的に安定しており、長期間使用しても劣化しにくいという特性を持っているため、従来のセンサーでは困難な過酷な環境でも高精度な測定が可能である。
|
||||
|
2023
堀場雅夫賞
|
2023
堀場雅夫賞
|
国立大学法人京都大学 大学院工学研究科 電子工学専攻
助教
|
研究題目
超ワイドギャップ半導体の基礎光物性解明と新機能性発現に向けた深紫外時空間分解分光法の開拓
|
半導体
|
|
半導体
次世代半導体デバイス材料として超ワイドギャップ(または超ワイドバンドギャップ※1)半導体材料に注目が集まっている。超ワイドギャップ半導体とはダイヤモンド、Ga2O3(酸化ガリウム)、およびAlN(窒化アルミニウム)に代表される極めて大きなバンドギャップ(禁制帯幅)を有する材料群のことであり、これらを用いた深紫外発光デバイス※2や超低損失・高耐圧パワーデバイスの実現が期待されている。しかしながら、例えば発光デバイスに着目すると、超ワイドギャップ半導体を用いた深紫外発光デバイスの発光効率※3は極めて低いのが現状である。石井氏は、超ワイドギャップ半導体の物性理解が未だ不完全であることがその一因と捉え、さらには超ワイドギャップ半導体の分析・計測技術の1つである深紫外分光技術※4が未成熟であることに着目した。そして、摂動※5(応力・電場)下深紫外分光法の開拓や世界最短波長で動作する深紫外近接場光学顕微鏡※6を開発することで、AlNの励起子構造※7を世界に先駆けて提案し、AlGaN(窒化アルミニウムガリウム)結晶に内在する発光性欠陥中心の発見などを行った。これらの超ワイドギャップ半導体基礎光物性と深紫外時空間分解分光法※8の開拓に関する研究は、今後の超ワイドギャップ半導体光電子デバイス開発を大きく加速することが期待される。1バンドギャップ:電子に占有された最も高いエネルギーバンド(価電子帯)の頂上と,電子に占有されていない最も低いエネルギーバンド(伝導帯)の底の間のエネルギー差。半導体の電気や光の性質を決める重要な要素。2深紫外発光デバイス:深紫外領域の光を放出するデバイス。深紫外領域は、波長が非常に短く、一般的な可視光よりもエネルギーが高い領域。3発光効率:デバイスが入力された電力に対して、どれだけ多くの光を出力できるかを示す指標。4深紫外分光技術:深紫外領域の光を使用して材料の性質を分析するための技術。材料が深紫外光にどのように反応するかを測定することで、材料の特性や構造を理解することができる。5摂動:外部から与えられる力や電場の変化のこと。摂動下では、材料の特性や挙動が変化することがある。6近接場光学顕微鏡:高分解能な顕微鏡で、光の回折による空間分解能の限界を超えて微小な構造を観察が可能。7励起子構造:半導体材料中で電子と正孔が結合した状態のこと。励起子は、光や電場などのエネルギーを吸収して生成され、特定のエネルギー状態を持つ。8深紫外時空間分解分光法:材料からの深紫外領域の光応答を時間軸・空間軸・エネルギー軸に分解して試料の物性を分析する手法。
|
||||
|
2023
堀場雅夫賞
|
2023
堀場雅夫賞
|
チューリッヒ工科大学 化学・応用バイオサイエンス学部
上級研究員
|
研究題目
チップ増強光分光法を用いた新規半導体材料のナノスケール化学特性評価
|
半導体
|
|
半導体
クマール氏の研究は、二次元遷移金属ダイカルコゲナイド※1と有機光起電力(OPV)※2デバイスという2つの半導体材料に対するナノスケールの解析に注目した点に特徴がある。二次元遷移金属ダイカルコゲナイドの研究では、単層MoS2※3とWSe2※4における励起子過程を調べるために、チップ増強光分光法(TEOS)※5を利用した。また、ハイパースペクトルチップ増強フォトルミネッセンスイメージングを用いて、単層のMoS2における励起子およびトリオン※6のマッピングにおいて、20nmという前例のない空間分解能を実証した。単層のWSe2については、TEOSとケルビンプローブフォース顕微鏡※7を組み合わせ、粒界の光電子挙動を50nmの分解能で明らかにした。OPVデバイスについては、TEOSと光伝導性AFM※8を組み合わせることで、STEOM※9と呼ばれる新しい手法を導入した。この革新的な手法により、20nm以下の分解能で、動作可能なOPVデバイスのトポグラフィー、化学組成、光電気特性を同時に評価することに成功した。クマール氏の研究の意義は、新規半導体材料のナノスケールでの特性評価と理解の発展にある。同氏は二次元遷移金属ダイカルコゲナイドとOPVデバイスにTEOSを適用することで、従来技術の限界を超えるTEOSの能力を実現した。その発見は、励起子プロセス、励起子およびトリオン集団の不均一性、粒界での光電子挙動、OPVデバイスの構造物性相関に関する貴重な洞察を提供し、次世代オプトエレクトロニクスデバイスと有機光起電力技術の開発と最適化に大きく貢献するものと期待される。1二次元遷移金属ダイカルコゲナイド:遷移金属元素(モリブデン、タングステンなど)と硫黄・セレン・テルルなどのカルコゲン元素からなる、二次元的な層状構造を持つ化合物。2有機光起電力(OPV/OrganicPhotovoltaic):有機半導体材料を用いて太陽光や光エネルギーを電気エネルギーに変換する技術。3MoS2:モリブデン(Mo)と硫黄(S)から構成される化合物。半導体の性質を持ち、光や電子の効率的な制御に用いられる。4WSe2:タングステン(W)とセレン(Se)から構成される化合物。半導体の性質を持ち、光や電子の効率的な制御に用いられる。5チップ先端増強光分光法(TEOS/Tip-enhancedOpticalSpectroscopy):微小なサンプル領域において光の相互作用を増強することで高い空間分解能や感度を実現する。6トリオン:励起子が「電子とホールの2粒子の束縛状態」であるのに対し、トリオンは、励起子にさらにもう1つの電子またはホールが結びついた「3粒子の束縛状態」。7ケルビンプローブフォース顕微鏡:表面の電位差や電荷分布を非接触で観察するための顕微鏡。8光伝導性AFM:光伝導性を持つ材料の表面の電気的な特性を非接触で測定するための技術。9STEOM(SimultaneousTopographical,Electrical,andOpticalMicroscopy):トポグラフィー(表面形状)、電気特性、光学特性を同時に評価するための新しい手法。
|
||||
|
2023
堀場雅夫賞
|
2023
堀場雅夫賞
|
マサチューセッツ工科大学 電気工学・コンピューターサイエンス学科
博士
|
研究題目
機械学習モデルによる単層MoS2のラマンとフォトルミネッセンスの相関の解明
|
半導体
|
|
半導体
高輝度でチューナブルなフォトルミネッセンス(PL)※1を有する二次元遷移金属ダイカルコゲナイドは、発光ダイオード、光検出器、単一光子エミッタなどのオプトエレクトロニクスおよびフォトニクス分野の新たなアプリケーションをもたらした。二次元材料の標準的な特性評価ツールの中でも、ラマン分光法※2は、材料の結晶性やドーピング、ひずみなど物質の特性を高速かつ非破壊で解析できる優れた技術である。しかし、その非線形性の強さゆえに、単層MoS2におけるPLスペクトルとラマンスペクトルとの相関を包括的に理解することは、依然として困難である。そこでルー氏は、PLの発光過程とラマン発光モードとの関連を系統的に調査探索し、PLとラマンの特性を関連付けることによって、物理的メカニズムについて包括的に考察した。また、機械学習モデルを複数のラマンスペクトルに適用し、ひずみとドーピングがもたらす効果をより深く解明した。まず、空間ラマン・マップ※3からPLマップを予測するためにDenseNet※4を導入し、さらに、SHAP※5を用いたXGBoost※6を適用して、個々のラマン特性がPL特性に与える影響を評価することによって、単層MoS2におけるひずみとドーピングの関連を解明した。さらに同氏は、PL特性をラマン周波数に投影するために、SVM※7を導入した。本研究は、二次元材料の特性評価に機械学習を適用するために必要な手法を提供し、より高効率のPLを可能にする二次元半導体の作製と調整のための知見をもたらすことが期待されている。1フォトルミネッセンス(PL):物質中の電子が光を吸収し、その物質特有の光を放出する現象。2ラマン分光法:物質中の結晶格子が光を吸収し、その物質特有の光を散乱する現象。散乱される光を分光し、周波数変化を測定して物質の特性を解析することができる。3空間ラマン・マップ:ラマン分光法を使用して得られるデータのうち、物質表面の異なる位置で得られたラマンスペクトルをマッピングしたもの。4DenseNet:畳み込みニューラルネットワーク。画像やパターンの特徴を学習するために使用される。畳み込みとは、画像内の局所的なパターンを検出する処理のこと。5SHAP(Shapleyadditiveexplanation):機械学習モデルの予測に対する特徴の寄与度を評価する手法。6XGBoost(gradient-boostedtreesmodel):勾配ブースティングと呼ばれる機械学習アルゴリズム。7SVM(SupportVectorMachine):機械学習アルゴリズム。分類や回帰などのタスクに使用される。
|
||||
|
2023
特別賞
|
2023
特別賞
|
国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻
教授
|
研究題目
シリコン光回路を用いた光電融合深層学習プロセッサの開発
|
半導体
|
|
半導体
竹中氏は、化合物半導体※1や相変化材料※2、二次元材料※3などの異種材料をシリコン光回路に集積したデバイスを実現し、光電融合深層学習プロセッサ※4に応用することを目指している。再構成可能なシリコン光回路(プログラマブル光回路)※5を用いた深層学習プロセッサは高速、低消費電力、低遅延で積和演算を実行できると期待されており、半導体微細化に依らず人工知能(AI)の性能を向上可能な次世代コンピューティング技術として世界中で研究が進められている。しかし、実用規模のプログラマブル光回路においては、回路中の光位相※6の精密な計測・制御および、光演算結果を低消費電力かつ高速に光電変換して読み出す計測技術が極めて重要となる。竹中氏は、化合物半導体や相変化材料をシリコン光回路に集積することで、光回路中の光位相や光強度を精密に計測・制御することに挑戦してきた。また、光回路上での誤差逆伝播※7による学習加速も可能な新たなプログラマブル光回路の実現に向けた研究にも取り組んでいる。これらの成果は、シリコン光回路を用いた深層学習プロセッサの早期実現に大きく資すると期待される。1化合物半導体:複数の元素で構成される半導体材料。異なる元素の組み合わせで高性能デバイスに使用される。2相変化材料:温度や圧力の変化によって物質の相(状態)を変える特性を持つ材料。3二次元材料:厚さが非常に薄く、表面が二次元的に構造化された材料。その厚さが原子や分子の単層や数層で構成される。4光電融合深層学習プロセッサ:光回路と電子回路を組み合わせた特殊な情報処理を行うために設計された集積回路。5再構成可能なシリコン光回路(プログラマブル光回路):プログラムによって光の流れを制御できるシリコン製の回路。6光位相:光の波の位置や進行方向の情報。7誤差逆伝播:ニューラルネットワークの学習手法で、誤差を逆方向に伝播させて重みとバイアスを調整することで、正確な出力を実現する方法。
|
||||
|
2023
特別賞
|
2023
特別賞
|
東海国立大学機構名古屋大学 大学院工学研究科 電子工学専攻
講師
|
研究題目
微細構造計測に向けた小型深紫外レーザー光源の開発
|
半導体
|
|
半導体
久志本氏は、微細化が進む半導体業界の技術革新を支える高分解能・高精細な測定システムに搭載が期待できる小型の深紫外半導体レーザー※1の実証と、室温での連続波発振の実現に成功した。レーザー光は、非接触・非破壊な光学的分析・計測手法で使用されている。特に、波長が短いほど微細な構造を捉えるため、短波長のレーザー光源はますます重要性を増している。その中でも、半導体レーザーは小型で高効率かつ低コストな光源として、検査システムなどに広く利用されているが、長年にわたり、深紫外光を発する半導体レーザーの実現には多くの課題が存在していた。そこで、単結晶AlN(窒化アルミニウム)基板※2を用いたAlGaN(窒化アルミニウムガリウム)結晶※3の欠陥低減と、従来手法とは異なる伝導性制御技術を用いて、パルス電流注入※4による深紫外半導体レーザーの実証を行った。さらに、多角的な評価のための測定システム構築を行い、デバイス性能の低下は欠陥形成が主な原因であることを明らかにした。そこで、レーザー結晶の形状制御による剪断応力※5の集中抑制手法を提案し、結晶欠陥抑制によって当初の1/10の電力で動作し、室温で連続波発振するレーザーを実現した。この成果は、深紫外半導体レーザー光源の実用化に大いに貢献するものである。1深紫外半導体レーザー:波長が紫外線よりもさらに短い光を発する半導体レーザー。紫外線により微細な構造の観察や特定の光応用技術に使用される。2単結晶AlN基板:窒化アルミニウムを単結晶として成長させた基板。高品質な半導体デバイスの作製に使用される。3AlGaN結晶:アルミニウム(Al)と窒素(N)とガリウム(Ga)から構成される化合物。4パルス電流注入:電流を短いパルス(パルスは一時的な電流の変化)で注入すること。デバイス内部で特定の効果や反応を引き起こすことができる。5剪断応力:物体や材料に力がかかったときに、その物体内部の層同士が相対的にずれる力。
|
||||
|
2022
堀場雅夫賞
|
2022
堀場雅夫賞
|
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科化学システム工学専攻
特任准教授
|
研究題目
原子分解能電子顕微鏡解析で先導する新しい窒素還元サイトのデザイン
|
水素
|
|
水素
水素の貯蔵・輸送に優れた水素キャリアとしてのアンモニア合成触媒・プロセスは、再生可能エネルギーの有効利用手段として注目されている。高活性な触媒開発のためには、活性点の構造と化学状態を解析して、新しいデザインへとつなげる必要がある。佐藤氏は、触媒開発において重要な大気非曝露下での収差補正透過型電子顕微鏡と各種分光検出器による観察・分析技術を組み合わせ、触媒の活性点を原子レベルで直接解析する手法を確立した。佐藤氏の研究は、触媒反応プロセスの技術革新に繋がる分析・計測技術として極めて重要である。この手法により、高活性アンモニア合成触媒に必要な窒素還元サイト(活性点)の構造と作用機構を明らかにし、さらなる高活性化や非貴金属化を達成するとともに、世界最高レベルの実用的な触媒を複数開発した。開発された分析・解析法は実際の触媒開発(デザイン)にも適用され、それらがアンモニアの水素キャリアとしての利用拡大と水素流通ネットワークの構築に繋がり、カーボンニュートラル社会構築に貢献すると期待される。
|
||||
|
2022
堀場雅夫賞
|
2022
堀場雅夫賞
|
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科電子工学専攻
教授
|
研究題目
触媒活性サイトの実空間イメージングに資する電気化学セル顕微鏡の開発
|
水素
|
|
水素
近年の水素需要の増加に伴い、プラチナなどの高価な貴金属に代わる水素の効率的な生成が可能な触媒開発が進められている。その触媒として注目されている二硫化モリブデン(MoS2)は、原子1層分の厚さのナノシートにすることで水素生成の優れた触媒になることが知られている。MoS2の触媒能の更なる向上のためには、触媒のどのような構造が活性に寄与しているかを知る必要があるが、従来の走査型電気化学顕微鏡では分解能の限界により、触媒能が向上する原理の詳細な理解には至っていない。高橋氏は現象の理解に最適な評価装置として、分解能を従来の十数μmから20~50nmへと大幅に向上した世界最高分解能の走査型電気化学セル顕微鏡(SECCM)の開発に成功した。さらにSECCMを用いた触媒活性部位の可視化(電気化学イメージング)により水素発生反応の効率が良いMoS2の構造を明らかにした。また、このSECCMは触媒自体の改変や劣化部位の特定、水素発生反応以外の触媒についての評価ができることから、光触媒や蓄電材料といった様々な研究への応用が可能であり、今後のエネルギー関連研究への貢献が期待される。
|
||||
|
2022
堀場雅夫賞
|
2022
堀場雅夫賞
|
東北大学多元物質科学研究所
准教授
|
研究題目
電気化学に基づく欠陥エンジニアリング技術の開発
|
水素
|
|
水素
カーボンニュートラルの実現に向けて、次世代型蓄電池や燃料電池などの高効率エネルギー貯蔵・変換技術は必要不可欠である。これらのデバイスを構成するエネルギー機能材料では材料中に存在する格子欠陥*が機能発現の源となることが知られている。中村氏は、固体電解質から成る電気化学セル*を用いて、電量滴定*により欠陥生成メカニズムを評価する手法を確立し、欠陥がどのように生成し、機能性にどのような影響を与えるか、その詳細を明らかにした。近年では、上記技術を応用した印加電圧や電気量による欠陥制御技術を開発し、材料開発に欠陥を積極利用することにも挑戦している。これまでに、蓄電材料への酸素欠陥の導入によりエネルギー密度維持率が飛躍的に向上することを見出すなど、新規な成果が得られ始めており、新たな材料開発コンセプトの確立とエネルギー機能材料の革新が期待される。*格子欠陥:結晶性材料における原子配列の乱れ。代表例として、空孔や置換イオン、格子間イオンなどが挙げられる。*電気化学セル:電解質、正極および負極などから構成される電気化学測定用の器具*電量滴定:電解によりイオンを発生させ、イオンと対象物質の反応が終了するまでに要した電解の電気量を測定することで、対象物質を評価する手法。
|
||||
|
2022
特別賞
|
2022
特別賞
|
九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
准教授
|
研究題目
太陽光をエネルギー源としたプラズモン誘起電荷分離による高効率水素発生システムの開発
|
水素
|
|
水素
髙橋氏は、従来よりも安価で安定、かつ高効率な、太陽光による水素発生システムの開発を目指している。太陽光は総量が大きく有望な資源であるが、単位面積あたりのエネルギー密度は小さく、供給量が不安定である。そのため、何らかの手段でエネルギーを貯める、その密度を高めるといった工夫を施すことが、実装においては重要な課題となる。髙橋氏は、金属ナノ粒子の局在表面プラズモン共鳴(LSPR)※によって、太陽光のエネルギー密度を高めるとともに、金属ナノ粒子と半導体とを組み合わせた時に生じるプラズモン誘起電荷分離(PICS)※を用いて、光のエネルギーを電気化学エネルギーに変換し、水素発生システム等に活用しようとしている。半導体は、従来系のn型半導体※の代わりにp型半導体を用いることで、安定性や電荷分離効率の改善が期待できる。また、金属ナノ粒子の構成金属や結晶面の制御によって、反応生成物の選択性向上も見込まれる。本研究は、光エネルギーを、高効率かつ安定的に、電気・動力・熱などのエネルギーへ変換して活用する技術として、エネルギー問題の解決に資すると期待される。※局在表面プラズモン共鳴(LSPR,Localizedsurfaceplasmonresonance):金属に光を照射した際、特定波長の光エネルギーが、金属ナノ粒子表面近傍の回折限界を超えたナノ空間に、時間的・空間的に局在化する現象。理論上は、光エネルギーを数十倍~数百万倍に捕集することが可能。※プラズモン誘起電荷分離(PICS,Plasmoninducedchargeseparation):LSPRを示すナノ金属と半導体を組み合わせることにより、共鳴波長の光照射化で、金属ナノ粒子の電荷が半導体に移動する現象。※n型半導体自由電子の移動よって電気伝導が起こる半導体。※p型半導体電子の欠損部である正孔(ホール)の移動によって電気伝導が起こる半導体。
|
||||
|
2022
特別賞
|
2022
特別賞
|
カールスルーエ工科大学ヘルムホルツ研究所 ウルム校
テニュアトラック教授
|
研究題目
相関分光法及び研究室規模製造によるデータ駆動材質発見の加速及びスケールアップ製作
|
水素
|
|
水素
シュタイン氏はエネルギーインフラの脱炭素化を実現できる技術を開発できるため、電池や電解機器に使用される高信頼性・高効率の材質の発見プロセスを加速することを目指している。材質の発見プロセスでは数百の複合材料にて試験を行うため膨大な計測、データ解析及び試験準備が必要であるため、材質の発見が数か月以上かかるものである。材質の発見を加速することは今でも重要な課題である。シュタイン氏は電気化学エネルギー貯蔵迅速研究プラットホーム(PLACES/R)を開発した結果から材質研究の自動化を実現した。このプラットホームは相互接続分析計(XRF、ラマン、FTIR、XPS等)、データ解析装置とロボットをデータサイエンスにより材質評価段階においても自動化を実現している。人工知能(AI)が評価目標や試験パラメーターを調整するため、研究者はより深い研究計画やデータ解釈を中心に作業を行うことができる。シュタイン氏が実現できた材質発見の自動化はエネルギー部門の脱炭素化におけるエネルギー材質研究の新世代をもたらす。
|
||||
|
2021
堀場雅夫賞
|
2021
堀場雅夫賞
|
大阪府立大学 大学院理学系研究科物理科学専攻 教授 (兼務)研究推進機構 LAC-SYS研究所
(RILACS)所長
|
研究題目
マイクロフロー光誘導加速による革新的バイオ計測技術の開発
|
ライフサイエンス
|
|
ライフサイエンス
医療や創薬・公衆衛生などの分野では、タンパク質や糖、疾患の原因となる物質や細菌など、生体由来試料の測定が不可欠である。しかし、従来の測定で用いられていた手法は煩雑な操作が必要なことが多く、高度な技術や高価な測定装置、長い実験時間が必要になるといった課題があった。飯田氏は、液体中の光応答性材料(基板、粒子)に光を照射すると周囲にあるタンパク質などの生体物質が集光部に向かう現象を利用し流路内の狭小空間で測定対象を濃縮・反応加速して測定するマイクロフロー型の光誘導加速システム(LAC-SYS)を開発した。これにより、従来法と比べて数十~数百倍高感度な測定が可能になり、極微量(fg※オーダー)のタンパク質をわずか数分間で定量評価することに成功した。本技術は医療や食品など様々な分野での幅広い応用が期待される。医薬品開発におけるスクリーニングや個別化医療における患者ごとの病態把握などが迅速・簡便にできるようになると考えられる。※fg:1gの1,000兆分の1
|
||||
|
2021
堀場雅夫賞
|
2021
堀場雅夫賞
|
東京大学 先端科学技術研究センター
准教授
|
研究題目
AI駆動型の高速細胞形態ソーター群とその応用開発
|
ライフサイエンス
|
|
ライフサイエンス
大量の細胞を、高精度かつリアルタイムに画像情報解析しながら分離できるセルソーター※1が長く望まれてきた。しかし顕微鏡を用いた細胞分離は低速であり、既存フローサイトメトリー技術※2で得られる情報は光強度総量に限定されているため実現は難しかった。太田氏が開発したゴーストサイトメトリー法は、「人を介さない画像解析には画像は必ずしも必要ない」という逆転の発想に基づいている。マイクロ流路中の細胞の動きを利用して細胞画像情報(信号)を得た上で、画像の再構成は行わずに直接AIで高速判別することで、高速・高精度な細胞の分離を実現した。この研究成果は、希少細胞を用いた医療診断、細胞解析に基づく創薬スクリーニングなど、バイオ・細胞医療分野への幅広い応用が期待されている。(※1)セルソーター:種々の細胞をそれぞれの特徴に基づき選択的に分取する装置。(※2)フローサイトメトリー技術:流体中を流れる細胞に光を当て、光散乱強度や蛍光強度を用いて分析する技術。
|
||||
|
2021
堀場雅夫賞
|
2021
堀場雅夫賞
|
東海国立大学機構 名古屋大学高等研究院・医学系研究科病態内科呼吸器内科
S-YLC特任助教
|
研究題目
近赤外光応答性細胞死誘導プローブの作用機構解明と治療効果計測基盤の構築
|
ライフサイエンス
|
|
ライフサイエンス
現在のがん治療に用いられている放射線療法や化学療法は正常な細胞にも大きな損傷を与え、副作用などによる患者の負担は非常に大きい。佐藤氏は近赤外光線免疫療法(NIR-PIT)と呼ばれる新しいがん治療法を研究している。本手法はがん細胞に結合する抗体に光(近赤外線)を照射すると反応する物質(プローブ)を付加したものを用いる。抗体を用いてがん細胞にプローブを運び、そこへ光を照射するとプローブが反応してがん細胞を破壊するという患者の負担が少ない手法である。NIR-PITの作用機構は長ら担が少ない手法である。NIR-PITの作用機構は長らく不明であったが、佐藤氏によってNIR-PITでがん細胞が破壊されるメカニズムが解明された。その成果から、今回用いたプローブの近赤外蛍光分光測定により細胞の破壊を計測・定量・予測できることが分かった。これらの成果はがんの診断・治療の両面に大きく貢献するものである。これらの成果を基に、本治療は世界に先駆けて日本で限定承認を受け、先進医療・保険診療として社会実装されている。
|
||||
|
2021
特別賞
|
2021
特別賞
|
東京農工大学 工学部化学物理工学科
准教授
|
研究題目
分光データを利用した医薬品生産プロセスのリアルタイムモニタリングと制御
|
ライフサイエンス
|
|
ライフサイエンス
近年、医薬品生産の高効率化のための新技術開発が求められている。その一環として、バッチ生産※から連続生産へ転換するための技術開発が進められているが、連続生産の実現には生産プロセス内の医薬品の情報をリアルタイムにモニタリングする技術が必要不可欠である。しかし、医薬品の品質をリアルタイムに直接測定することは困難であることが多い。また、従来の近赤外スペクトルから医薬品の品質を予測する手法には、予測精度が経時的に低下するなどの欠点があり、生産プロセスでの活用には課題があった。金氏は、近赤外スペクトルから医薬品の品質を安定的かつ高精度に予測する手法の開発を目的に、データサイエンスの技術を活用した新たなデータ解析手法を開発した。本手法を用いたリアルタイムな品質管理・制御を行うことで、コスト削減にとどまらず、環境負荷や事故リスクの低減も可能となり、医薬品生産プロセスの効率化を実現することが期待される。※各工程が独立し、一つの工程終了後に生産物をサンプリングして品質を確認し、次の工程に移行する生産方法。
|
||||
|
2019
堀場雅夫賞
|
2019
堀場雅夫賞
|
テクニオン - イスラエル工科大学 電気工学部
助教
|
研究題目
次世代の電力網および電気自動車のためのエネルギー貯蔵装置の最適制御
|
電力・電池
|
|
電力・電池
電気自動車や再生可能エネルギーの普及が進んでいる。電力の需給バランスを取り、エネルギーを無駄なく使うためには、二次電池をはじめとするエネルギー貯蔵装置の利用が要になる。しかし、エネルギー貯蔵装置にいつエネルギーを貯め、いつ供給すればよいか判断することは非常に難しい。レブロン氏は、エネルギー貯蔵装置の重要性にいち早く着目し、複雑な電力網において最高のエネルギー効率を実現できるエネルギー貯蔵装置の最適コントロールの決定方法を開発した。この技術論文は多くの研究者に引用されており、世界の先駆けとなっている。この手法を使えば、余剰エネルギーを蓄え、必要時に供給する最適化された充放電スケジュールを精度よく求めることができる。この研究は、電気自動車や再生可能エネルギーの有効利用に大きく貢献でき、より大規模で複雑な電力網への応用が期待される。
|
||||
|
2019
堀場雅夫賞
|
2019
堀場雅夫賞
|
九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
助教
|
研究題目
電気自動車、電力網およびそれらの相互作用のための機械学習とマルチエージェントシステムに基づく制御および最適化手法
|
電力・電池
|
|
電力・電池
再生可能エネルギーを活用する電力網において、電力需給バランスの安定化、電力需給量の急変への対応力、各家庭や地域での活用が期待されるバッテリーに代表される蓄電システムの最適な利用等、多くの課題がある。グエン氏は、それらの課題を解決するため、バッテリーの状態把握と制御、データからパターンを見つける機械学習による電力の需給予測や最適な需給調整機能をマルチエージェントシステム※上に分散配置する手法を考案した。この手法では、車載バッテリーから家庭内/地域内/地域間にいたるまでの幅広い電力需給マネジメントがエージェント単体、または、それらの連携で実行され、その一貫した設計・運用手法は今までにないアプローチと言える。この研究により、再生可能エネルギー活用での課題や緊急時の電力供給の課題など、将来のエネルギーネットワークの諸問題解決の見通しが得られた。(※)マルチエージェントシステム:エージェントとは管理したい対象毎に設けられる機能単位。マルチエージェントシステムは、そのエージェントが他のエージェントと連動する分散処理システム。
|
||||
|
2019
堀場雅夫賞
|
2019
堀場雅夫賞
|
京都大学大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻
准教授
|
研究題目
パラメータ感度プロットの開発とリチウムイオン二次電池のモデリングへの応用
|
電力・電池
|
|
電力・電池
あらゆるものが繋がる第四次産業革命後の次世代社会では、複雑なネットワークで実現されるシステムが重要な役割を担う。そのようなシステムを適切に制御するためのモデリング※においては、実システムと同等の複雑さを持つモデルの利用は非現実的であり、シンプルかつ必要な精度を持つモデルを構築しなければならない。したがって、モデルのシンプルさと精度のバランスをより精密に評価する技術が必要となる。丸田氏は、この問題を解決するために、モデルのシンプルさと精度のバランスを周波数領域で可視化する「パラメータ感度プロット」の技術を創出した。さらに、この技術を二次電池に応用し、二次電池の充電率や劣化具合を推定するための精度が良く信頼性が高いモデルを開発、合理的なモデル化指針を与える新しい考え方を示した。この研究は、二次電池のみならず、今後社会が直面する次世代の複雑なシステムのモデル設計への貢献が期待される。※モデリング:対象の構造や物理現象を数学的に定式化すること
|
||||
|
2019
特別賞
|
2019
特別賞
|
東京工業大学 物質理工学院応用化学系
助教
|
研究題目
太陽光発電を主力とする分散グリッド実現のための水素技術の導入、制御法の構築
|
電力・電池
|
|
電力・電池
CO2排出ゼロに向け再生可能エネルギーや水素社会への移行が進む中、各地で様々な規模の発電・電力ネットワークが導入されつつある。しかし、不規則に変動する再生可能エネルギーは大規模系統電力ネットワークの安定化に負担をかけるため、それを低減するために中小ネットワークへ蓄エネルギー技術の導入が有力候補となる。長谷川氏は、東京工業大学が持つ1万kW規模の電力ネットワークでの分単位から年単位の膨大な実データを多角的に分析し、水素蓄エネルギー技術※1導入による安定化と低コスト化に対する効果を明らかにした。さらに、水素蓄エネルギーのための燃料電池/電解セル※2(SOFC/EC)技術における水の電気分解反応を予測できるモデルを構築し、性能向上により将来有望な技術になる可能性も明らかにした。この研究は、今後、エネルギーマネジメントと要素技術、マクロ/ミクロの両視点から、各電力ネットワークが調和しながら電力供給を行う新しいシステム制御技術への貢献が大きく期待される。(※1)水素蓄エネルギー技術:水を電気分解するなど、エネルギーを使用して水素を生成することで、エネルギーを水素に変換し、貯蔵しておく技術(※2)電解セル:電気分解反応を行うための正極・負極・電解液が1組で構成されたもの
|
||||
|
2019
特別賞
|
2019
特別賞
|
コロンビア大学 電気工学科
助教
|
研究題目
データ駆動型モデリングとリチウムイオン電池特性の評価
|
電力・電池
|
|
電力・電池
リチウムイオン電池の残量を正確に把握することは電気自動車の普及にとって重要な課題となっている。これまで、電池の挙動を定式化した電池モデルを用いて残量を推定する研究は行われてきたが、電池のメカニズムは未解明な部分があり、実際の温度や使用条件では推定誤差が大きくなる課題があった。プレインドル氏は、既存のモデルを用いずデータから規則性や判断基準を自動的に学習する新たな残量の推定手法を考案した。推定誤差の原因ともなる環境の影響を受けない新規手法では、幅広い温度域(-25〜45℃)における誤差が1%以下となる高い精度での推定に成功し、電気自動車に搭載するシステムで実用的に活用できる可能性を切り拓いた。この研究は、電池寿命の推定にも応用することができ、電池の最大限かつ効率的な活用への大きな貢献が期待される。
|
||||
|
2018
堀場雅夫賞
|
2018
堀場雅夫賞
|
京都大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻
助教
|
研究題目
レーザー干渉計によるプラズマ電子密度計測の高速・高精度化
|
半導体
|
|
半導体
半導体製造プロセスに用いられる熱的に平衡していない状態のプラズマ(※1)は、電子の衝突による電離(※2)・励起(※3)がプラズマ状態の持続や化学反応に影響を与えるため、プラズマ中の電子密度を測定することは重要である。しかし、電子密度を測定する手法の一つであるレーザー干渉計(※4)には、近年に開発されているプラズマ源に対して、時間・空間分解能や検出感度などが十分ではないという課題がある。占部氏はレーザー干渉計とミリ波吸収法(※5)を組み合わせ、近赤外レーザーと顕微鏡を用いた干渉計などを開発し、電子密度計測の高速化、高空間分解能化、高電子密度分解能化を実現した。将来的には、開発されたレーザー干渉計が半導体プラズマ装置に組み込まれ、プロセスの最適化やプラズマ異常の検知を実現し、半導体製造プロセスの高精度な制御や歩留まり向上に貢献することが期待される。※1気体を構成する分子が電離しイオンと電子に分かれて運動している状態※2原子や分子が電子を放出または取り入れてイオンになること※3原子や分子などが外部からエネルギーを得て、高いエネルギーをもつ状態に移ること※4一つの光源から出るレーザーを二つまたはそれ以上に分け、再び集めた時にできる干渉縞(位相差)を観測して、状態を調べる装置※5ミリ波をプラズマに照射し、それに対する反応を計測する手法
|
||||
|
2018
堀場雅夫賞
|
2018
堀場雅夫賞
|
名古屋大学大学院 工学研究科 プラズマナノ工学研究センター
助教
|
研究題目
高精度半導体プラズマプロセスのための基板温度計測システムの開発
|
半導体
|
|
半導体
半導体デバイス製造プロセスで求められる原子レベルの加工の再現性を実現するためには、半導体ウエハ(基板)の温度を正確にモニタリングし制御することが重要である。しかし、様々な外乱が存在するプロセス中のウエハの温度を高精度にモニタリングすることは困難であり、特に光干渉計(※)を用いる場合は、周囲の装置からの振動の影響をいかに抑えるかが課題であった。堤氏は、計測対象となる半導体ウエハが高い平行度をもち、鏡面研磨が施されていることに着目し、ウエハの表面と裏面で反射する光の干渉から温度を算出する手法を発案した。この手法は従来の手法とは異なり、同経路を伝搬する光の干渉を使用する。そのため、周囲からの振動の影響を受けにくく、高精度に温度を測定することができる。本技術は、製造工程中のウエハ温度を高精度で高速にモニタリングするものであり、製造工程の歩留まり向上に大きく貢献すると期待される。※一つの光源から出る光を二つまたはそれ以上に分け、再び集めると干渉という現象が生じる。この干渉光には、分岐された光が通った経路の屈折率や長さの情報が含まれる
|
||||
|
2018
堀場雅夫賞
|
2018
堀場雅夫賞
|
独立行政法人 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター
主任研究員
|
研究題目
半導体プラズマプロセス中の薄膜材料の欠陥検出
|
半導体
|
|
半導体
半導体製造プロセスではプラズマ技術を用いてシリコンウエハ上への材料膜の堆積や不要な部分の除去が繰り返し行われる。材料膜の特性は半導体デバイスの性能に大きく影響を与え、高性能化にはプロセス条件を緻密に制御することが求められるが、プロセス中のプラズマの状態と材料膜の特性との関係は十分に解明されていない。布村氏は波長の異なる2種類の光を材料膜に照射して得られる光電流(※)の増減をリアルタイムに測定することにより、半導体デバイスの性能を低下させる材料膜の欠陥をリアルタイムに検出する技術を開発し、プラズマの状態が材料膜の特性に及ぼす影響をプロセス中に計測する研究を進展させた。本研究は太陽電池で使われるアモルファスシリコンの膜を形成するプロセスを対象としているが、他のプラズマ技術を用いるプロセスにも適用される事が期待される。※物質に光を当てたとき,その光を吸収して光電子と呼ばれる自由電子を生じる。この光電子の運動による電流を光電流という。
|
||||
|
2018
特別賞
|
2018
特別賞
|
ルール大学ボーフム(ドイツ) プラズマ・原子物理学科
上席研究員
|
研究題目
イオンの速度分布関数による非侵襲的プラズマ特性解析
|
半導体
|
|
半導体
半導体製造プロセスにおいてプラズマの状態を把握し、制御する事は半導体製造プロセス上で重要となる。しかし、実際の現場ではプラズマの発生環境を乱すことなく、イオンの種類や密度などのプラズマの特性を得ることは困難である。質量分析計はプラズマの発生環境を乱すことなくプラズマ中のイオン種、エネルギー分布、密度等の情報を得る方法の一つであるが、分析計付近の情報しか得られない。ツァンコフ氏は、質量分析計を用いて測定するイオン速度の分布等がボルツマン方程式(※)の理論に基づいているという解析事例を調査し、プラズマの特性をより正しく推定する方法を提案している。簡便にプラズマを測定する手法は半導体製造プロセス上、極めて重要であり、今後、プラズマの定量的な特性を解明する手法として利用されることが期待される。※気体分子の速度分布を示す方程式
|
||||
|
2017
堀場雅夫賞
|
2017
堀場雅夫賞
|
九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門
助教
|
研究題目
水中の溶存物検出に向けた電流・光応答に基づく小型分析系の開発
|
半導体
|
|
半導体
環境水や土壌の汚染は、現在においてもなお、潜在的な世界的課題となっている。そのため、その場で水の安全性を確認できる簡便な測定法が求められている。石松氏は、イオンの移動電流に着目し、水中の親水性マイナスイオンを高感度に分析できる原理を考案するとともに、水中のプラスイオンを高選択的に多成分同時検出できる「電流応答型イオン選択性電極」を新たに開発した。さらに、有機ELと有機フォトダイオードを応用して、イオン移動に基づく検出が難しい中性物質、たとえば非イオン性界面活性剤をppbレベルまで定量できる分析システムを構築した。これらの分析システムは小型化が可能であり、「その場」分析に適したポータブル測定装置として、世界各国における環境水中の汚染物質測定に貢献することが期待できる。
|
||||
|
2017
堀場雅夫賞
|
2017
堀場雅夫賞
|
独立行政法人 産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門
主任研究員
|
研究題目
測定対象の多様化に向けたスパッタナノカーボン薄膜電極の開発
|
水計測
|
|
水計測
電気化学測定法は、分子の酸化還元反応の際に流れる電流や電極界面の電位を測定することで、対象物質を検出する手法である。簡便・安価な検出手法として期待される一方、測定できる電位範囲が狭く微量物質の検出も困難であることから、測定対象となる物質が限られる点が課題とされてきた。加藤氏はカーボン薄膜材料※の精緻な設計により、従来電極では検出できなかった全核酸塩基などの生体分子、ビタミンEなどの抗酸化物質、ヒ素などをきわめて高感度かつ再現性良く測定できる「スパッタナノカーボン薄膜電極」を開発した。本研究は電気化学法の適用範囲を拡大するものであり、飲料・食品・環境・生体といった多くの分野における実用化が期待される。さらに、これまで電気化学的な分析が困難であった物質の標準定量法となり得る技術としても注目される。※カーボン薄膜材料:構造制御によりグラファイトのような高い導電性とダイヤモンドのような硬度を併せ持ったナノカーボン薄膜
|
||||
|
2017
堀場雅夫賞
|
2017
堀場雅夫賞
|
大阪府立大学 大学院工学研究科 応用化学分野 准教授
LAC-SYS研究所(RILACS) 副所長
|
研究題目
水中細菌計測のための細菌表面構造転写技術の開発
|
水計測
|
|
水計測
細菌による食中毒や感染症の防止は、飲料水や食品の安全・安心を確保する上で重要である。ただし、これまでの細菌検出法は測定に数日かかってしまうだけでなく、煩雑な前処理や技術的な熟練も必要とするのが普通であった。床波氏は、細菌の表面化学構造を精巧に写し取った「細菌鋳型膜」の合成方法を確立した。さらに、この細菌鋳型膜と、細菌の動きを制御できる誘電泳動法とを組み合わせることにより、まったく新しい発想の細菌検出法を開発した。この方法では目的とする細菌の検出がわずか数分で可能で、従来法に比べて大幅な時間短縮に成功した。細菌鋳型膜の特徴から、非常に選択性の高い検出手法としても注目される。迅速かつ高選択的な細菌検出方法として、厳密な衛生管理が求められる浄水場や食品産業全般における細菌検出システムへの活用が期待される。
|
||||
|
2017
特別賞
|
2017
特別賞
|
メリーランド大学 環境科学センター チェサピーク生物学研究所
准教授
|
研究題目
淡水および海水中の溶存有機物および汚染物質の光分解性の半連続的評価
|
水計測
|
|
水計測
水中の溶存有機物は、水中におけるさまざまな生物的・化学的プロセスに影響を及ぼすことから、水質を表す指標の一つとなっている。溶存有機物のうち、蛍光を発する性質をもつものは「蛍光性溶存有機物(CDOM)」と呼ばれ、その分解過程では光分解によるものが重要である。ゴンジオール氏は、太陽光を模擬した光を照射しながらCDOMの光学特性を半連続的に観察できる、新しい光分解システムを構築することに成功した。さらにこの独自のシステムを用いて、海水や湖水中のCDOMや汚染物質の挙動の解明を試み、CDOMの光学的な経時変化や他の水質指標との関係性を初めて明らかにした。この研究は、環境および生態系に密接に関係する溶存有機物の評価方法として、水質の保全・改善に有効な情報提供に繋がるものと期待できる。
|
||||
|
2016
堀場雅夫賞
|
2016
堀場雅夫賞
|
兵庫県立大学 大学院工学研究科・電子情報工学専攻
准教授
|
研究題目
超広帯域レーダを用いた人体の超高速立体イメージング
|
水計測
|
|
水計測
超広帯域レーダ※を用いた物体形状イメージングは、物体の検知手段として有効な技術のひとつであり、地中探査などで実用化されている。しかし、レーダから得た情報をコンピュータで画像化する処理時間が問題となり、自動運転には応用されてこなかった。阪本氏は、空気中の物体を計測するときに適用できる、新しい物体形状イメージング技術「SEABED法」を開発した。この手法は、従来の手法と比較して約100倍高速で、さらに人体形状も明瞭にイメージングできる高い分解能を有する。歩行者の認識技術として、人命を最優先する安心・安全な自動運転技術、さらには交通システムの構築に貢献することが期待される。※超広帯域レーダ:近距離の物体を高い分解能で計測できるレーダ。夜間や逆光などの悪環境下でも使用できる特長をもつ。
|
||||
|
2016
堀場雅夫賞
|
2016
堀場雅夫賞
|
金沢大学 新学術創成研究機構 自動運転ユニット
准教授
|
研究題目
市街地における完全自動運転を実現するハイディペンダブルローカライゼーション手法の開発
|
自動運転
|
|
自動運転
市街地における自動運転では、複雑な道路環境を確実に認識するため、高精度な地図に自己位置推定手法を組み合わせる必要がある。自己位置推定手法としてGPS等の衛星測位システムが実用化されているが、自動運転に使用する場合、ビル街やトンネル内など十分な精度が得にくい環境があることが問題となる。菅沼氏は、衛星測位に依存しない新しい自己位置推定手法「ハイディペンダブルローカライゼーション手法」を開発した。2次元オルソ画像※を地図として用い、車載センサ情報と照合する手法で、誤差約14cmの高精度を実現している。また、データ量が小さく、演算時・記録時の取り扱いやすさも大きな利点である。量産化への取り組みと公道での実証実験も始まっており、安全快適な移動や高齢過疎地域の次世代モビリティに大きく寄与することが期待される。※オルソ画像:上空から道路面を見下ろしたような画像
|
||||
|
2016
堀場雅夫賞
|
2016
堀場雅夫賞
|
東京農工大学 大学院工学研究院 先端機械システム部門
准教授
|
研究題目
リスク予測運転知能モデルに基づく協調型運転支援システム
|
自動運転
|
|
自動運転
自動運転技術には、運転の快適性向上と並んで、交通事故の防止効果といった安全性能も期待されている。ただし、現行の運転支援技術は、それにはまだ不十分であるのが現実である。ラクシンチャラーンサク氏は、熟練ドライバの運転知能「先読み運転モデル」をベースに、交通事故リスクを最小にする規範運転操作を導き出し、ハンドルやペダルに最適な反力を発生させるなどしてより安全な運転へと誘導する手法を提案した。運転者の状態や個人特性に適合する協調型の制御手法は、自動車運転技術としてはもちろん、ロボットや家電のインターフェイスにも応用可能な技術として期待される。
|
||||
|
2016
堀場雅夫賞
|
2016
堀場雅夫賞
|
東京大学 高齢社会総合研究機構
特任研究員
|
研究題目
リーンなセンサによる自動運転のための外界環境認識技術
|
自動運転
|
|
自動運転
高齢社会の到来により、高齢ドライバの運転支援の重要性が増している。これまでに開発された関連技術の多くは高速道路など自動車専用道路を想定したものであり、また、高価なセンサが用いられることから、実社会での普及は難しかった。伊藤氏は、車載センサと地図情報を組み合わせて活用することで、必ずしも十分整備がされていない生活道路を対象に、擦れ等の生じた停止線や横断歩道、規制速度表示などを検出する技術を開発した。この技術では、車載カメラなど、必要十分な機能だけをもった適正なセンサ類を採用していることも特徴である。実際に市販車に搭載されることにより、特に高齢者の生活環境での移動を支援し、活力あふれる社会の実現に寄与することが期待される。
|
||||
|
2016
堀場雅夫賞
|
2016
堀場雅夫賞
|
オハイオ州立大学 土木・環境・測地工学部
准教授
|
研究題目
地図情報システムを活用したユビキタス位置認識法
|
自動運転
|
|
自動運転
現在の主要な位置特定技術であるGPSは、自動運転への適用を考えた場合、位置精度・データ欠損などが課題となっている。イルマズ氏は、地図情報システム(GIS)として利用可能な公共の道路情報をグラフとしてモデル化し、車載センサ類や「ビジュアルオドメトリ」による走行軌跡推定と組み合わせることで、GPSが使用できない環境で位置特定する新しい方法を提案した。この位置特定技術は、単眼カメラと、メモリ容量の小さい小型モバイルコンピュータで実現可能である。どんな環境でも広範に適用できることから、GPSの補助またはGPSの代替となりうる技術として期待される。全地球測位システム(GPS):専用の人工衛星からの信号に基づき、現在位置を知るシステム地図情報システム:コンピュータネットワーク上で公開される、地図に各種の地理情報を重ね合わせたデータベースビジュアルオドメトリ:カメラの画像情報から、視覚的に移動量を推定する方法
|
||||
|
2015
堀場雅夫賞
|
2015
堀場雅夫賞
|
京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科
准教授
|
研究題目
動的超音波散乱法による懸濁微粒子溶液のダイナミクス解析
|
ナノ粒子
|
|
ナノ粒子
溶液中に分散したナノ粒子の粒径や分散状態を計測するには、試料にあてた光が粒子によって散乱する様子をみる「動的光散乱(DLS)法」が一般的である。ただし、粒子濃度の高い不透明な試料では光が透過しないため、DLS法の応用は困難であった。則末氏は、光の代わりに「超音波」を試料に照射する「動的超音波散乱(DSS)法」をこのような高濃度試料に適用し、さらに当初マイクロメートル(μm)オーダーであった検出下限を数十ナノメートル(nm)まで伸ばすことに成功した。加えて、超音波を様々な波長成分に分解することで、空間情報の取得や運動様式の識別も可能である。この研究は、インクや半導体粒子、機能性ゲルなど不透明な分散系の構造・分散状態の解析への応用が期待される。
|
||||
|
2015
堀場雅夫賞
|
2015
堀場雅夫賞
|
関西学院大学 理工学部 環境・応用化学科
助教
|
研究題目
ナノ光ファイバを用いた蛍光性ナノ粒子の一粒子計測
|
ナノ粒子
|
|
ナノ粒子
蛍光性ナノ粒子の一粒子計測技術は、光通信や生体組織の観察など幅広い応用が期待されている。しかし、計測機にナノ粒子からの光を効率よく集めることが困難であった。藤原氏は、直径300ナノメートル(nm)という極細のナノ光ファイバの作製に成功し、その表面に蛍光性ナノ粒子を接触させることで、ナノ粒子から生じた光子を効率よく集める手法を世界に先駆けて確立した。この方法による一粒子蛍光検出は、従来の手法に比べて約10倍の集光効率を達成している。この研究は、高効率集光デバイスとして、量子情報科学や生命科学の分野における新しいセンシングへの応用が期待される。※ナノ光ファイバ:通常の光ファイバを、直径が数百ナノメートル(nm)まで微細化したもの。※蛍光性ナノ粒子:半導体人工原子(量子ドット)に代表される、特定の波長に強い蛍光を示す粒子。
|
||||
|
2015
堀場雅夫賞
|
2015
堀場雅夫賞
|
名古屋大学 先端ナノバイオデバイス研究センター
特任講師
|
研究題目
量子ドット蛍光計測・元素分析による移植幹細胞 in vivo イメージング診断法の構築
|
ナノ粒子
|
|
ナノ粒子
再生医療として注目を集めている幹細胞移植において、生体内へ移植した後の細胞を追跡する技術は極めて重要である。しかし、移植細胞は小さいため、これまでの一般的な測定機器(レントゲン、CT、MRIなど)では、十分な追跡ができなかった。湯川氏は、「量子ドット」を幹細胞に効率よく取り込ませる技術を確立し、近赤外領域の蛍光を発する量子ドットを使用することで、移植後の幹細胞の長期にわたる定量的な追跡を実現した。さらに、蛍光の波長がそれぞれ異なる量子ドットを組み合わせ、移植された細胞を判別することも可能にした。この研究は、iPS細胞に代表される幹細胞の移植技術の進歩に貢献すると期待される。※量子ドット:主に半導体材料からなるナノ粒子であり、電子がナノ空間に3次元全ての方向から閉じ込められた状態のものをいう。決まった波長の光(励起光)をあてることで、強い蛍光を発する。また、同じ励起光をあてた場合でも、量子ドットの粒径により放出される蛍光の波長が異なるという特徴を持つ。※幹細胞:組織・臓器に特有な細胞に変化する前の「未分化」の細胞。他の種類の細胞に変化する能力を持つ。※invivo:「生体内」を意味する。
|
||||
|
2015
特別賞
|
2015
特別賞
|
パデュー大学 ブリック・ナノテクノロジー・センター(米国・インディアナ州)
准教授
|
研究題目
グラフェン・ナノ物質の顕微ラマン分光解析
|
ナノ粒子
|
|
ナノ粒子
炭素系ナノ材料として期待されるグラフェンの実用化には、詳細な物性情報の把握が不可欠である。チェン氏は、グラフェンそのものや、グラフェンでできた電子部品の物性評価を目的に、試料の温度・圧力・電流制御など専用の機構を備えたラマン顕微鏡を構築し、グラフェンのCVD膜成長やグラフェンの物性を解析することに成功した。あわせて、大面積グラフェン、単結晶グラフェンや二層グラフェンなど、電子部品への応用により適したグラフェンの開発でも成果をあげている。今後、さらに高品質で優れた特性をもつ特殊なグラフェンの開発など、グラフェンの実用化や新たなナノマテリアルの開発に貢献することが期待される。※グラフェン(Graphene):炭素原子が蜂の巣のような六角格子の形で結合して、一層のシート状の形をとったもの。非常に電気を伝えやすい(電気伝導度が高い)ことをはじめ、電子部品の材料として期待される多くの特長をもつ。※ラマン顕微鏡(Ramanmicroscope):試料にレーザ光をあてたときに放出される「ラマン散乱光」を利用し、分子の構造を調べる手法を「ラマン分光」という。ラマン顕微鏡では、試料の極めて狭い領域にレーザをあてて、局所的なラマン分光解析が可能。※CVD(化学気相成長):ガスを原料として、基板表面や気相中で化学反応によって薄膜を成長させる手法。
|
||||
|
2014
堀場雅夫賞
|
2014
堀場雅夫賞
|
カリフォルニア大学 サンディエゴ校 化学・生化学科
助教
|
研究題目
海洋表面における反応の直接測定のための高感度化学イオン化質量分析計の開発
|
ガス計測
|
|
ガス計測
大気中には様々な物質が含まれており、その生成や反応メカニズムを解析することは、大気汚染防止に非常に重要である。大気中の極微量の物質を現場で測定するためには、物質に電荷を与え、交流電圧と直流電圧を加えながらそれらの質量によって分離・測定する四重極質量分析計(QMS)がよく用いられているが、従来のQMSでは感度や分解能が不十分であり、海洋表面における窒素酸化物の反応メカニズムについては、実測定に基づいた研究が十分になされていなかった。バートラム氏は、化学反応によって物質に電荷を与え、それらの飛行速度によって物質を分離・測定する化学イオン化飛行時間型質量分析法(CI-TOFMS)を用いて、現場で、高感度かつ高分解能な測定を可能とするシステムを開発した。このシステムを用いて、海洋表面における窒素酸化物の反応を直接測定することによって、海洋表面が窒素酸化物反応に重要な役割を果たしていることを示唆した。この研究によって、これまで実測の難しかった大気中の諸現象のメカニズムが解明され、大気環境の正確な把握・予測ができるようになることが期待される。
|
||||
|
2014
堀場雅夫賞
|
2014
堀場雅夫賞
|
埼玉大学大学院 理工学研究科
准教授
|
研究題目
周波数可変ギガヘルツ光周波数コムを用いた超高分解スペクトル計測システムの研究
|
ガス計測
|
|
ガス計測
測定対象に光を当ててその性質を調べる測定法(分光法)では、広い周波数範囲で、かつ細かい周波数刻みで計測できれば、より多くの対象を詳細に分析できる。光周波数コム※はこのような計測を可能とする技術として近年注目されている。しかし従来の光周波数コムによる分光法では、各コムの周波数が離散的な一定値であるため、計測に有効に利用できる周波数が限られていた。塩田氏は、従来とは異なる光周波数コム発生機構を採用することで、各コムの周波数間隔を従来の100倍程度に広げ、かつ光通信分野で用いられている技術を応用して、周波数を連続的に変化させて、コム間の周波数もすべて利用できる技術を開発した。これにより、従来以上の広い周波数範囲と細かい周波数刻みでの分光計測が可能となる。本技術は、工業プロセスや自動車の排ガスといった多くの成分が混在したガスを成分ごとにリアルタイムで計測する必要がある分野などで、技術革新をもたらすことが期待される。※光周波数コム:非常に正確な一定の間隔の周波数を持つ光が多数集まった光源のことで、各周波数の光を櫛(=comb)の歯にたとえて名づけられ、精密な分光計測への応用が期待される技術として、この開発に対し、2005年にはノーベル賞が与えられた。
|
||||
|
2014
堀場雅夫賞
|
2014
堀場雅夫賞
|
大阪府立大学大学院 工学研究科 応用化学分野
准教授
|
研究題目
大気中二酸化窒素濃度の高確度連続計測
|
ガス計測
|
|
ガス計測
大気中の二酸化窒素のモニタリングは、二酸化窒素を一酸化窒素に変換器*1にて変換し、一酸化窒素を測定する化学発光法*2により行われています。定永氏は、この二酸化窒素濃度をより正確に測定するために、LED光を二酸化窒素に直接照射し、二酸化窒素を一酸化窒素に高選択的に変換する方法ならびに、二酸化窒素から生じる光を直接測定する方法(LED誘起蛍光法*3)を用いた連続計測装置の開発に成功しました。また、実用化に向けた長期モニタリングにも成功しました。この研究成果により、オゾンや酸性雨の原因物質として重要な二酸化窒素の濃度の高確度なモニタリング、ひいては地球環境に影響を及ぼすオゾンなどのガス状物質のより詳細な動態解明が期待されます。*1変換器:二酸化窒素を一酸化窒素に変換させる装置 *2化学発光法:一酸化窒素とオゾンを反応させた際に生じる光の強さを測定して、その強度から一酸化窒素濃度を求める方法*3LED誘起蛍光法:二酸化窒素に青色の可視光線を照射した際に生じる光の強さを測定して、その強度から二酸化窒素濃度を求める方法
|
||||
|
2014
特別賞
|
2014
特別賞
|
ケンブリッジ大学 化学工学科
|
研究題目
非線形トモグラフィー:燃焼解析のための新たなイメージング理論
|
ガス計測
|
|
ガス計測
トモグラフィーとは断層影像法のことであり、病院で患者に用いられるCTスキャンのように、対象の内部情報を得る技術である。この技術をガス濃度計測に応用すれば、空間でのガス濃度分布がわかる。しかしながら通常のトモグラフィーでは一つの分布情報しか得られないため、ガス濃度を求めるときは、圧力などの他の変数は全体で一定と仮定しなければならず、現実とのずれがあった。また使える計測手法が限られ、感度に限界のある一成分の濃度分布しか得られなかった。ツァイ氏は、通常のトモグラフィーを発展させた非線形トモグラフィーと、レーザーを用いた最新のガス計測手法とを組み合わせることを提案し、複数成分のガス濃度に加えて温度と圧力の分布など複数の情報の同時解析が可能であることや、より高感度のガス濃度分布計測が可能であることを示した。この手法を用いることで、エンジン内部のような不均一で高速に変化する環境の、ある一瞬の温度・圧力・ガス濃度分布や微量成分の分布が測定可能となり、自動車業界など、燃焼を扱う産業界で特に期待される。
|
||||
|
2013
堀場雅夫賞
|
2013
堀場雅夫賞
|
東京理科大学 理学部第一部化学科
教授
|
研究題目
電子を用いた新しい水計測法の開発とその応用
|
水計測
|
|
水計測
ラマン分光法は、試料にレーザ光を照射して分子の構造を調べる分析手法であり、多くの分野で使用されている。しかし、得られる信号強度が極めて微弱なため、産業的な水計測への応用は難しかった。由井氏は、強いレーザパルス光を水溶液に照射し、放出された電子の作用でラマン散乱強度が過渡的に最大10万倍まで増強される「電子増強ラマン散乱」を発見した。さらに、この電子増強ラマン散乱を利用して、発光などの妨害に強く一度きりの励起でラマンスペクトルを計測できる新しい方法を開拓した。この手法は、水溶液の表面や超臨界水など、特殊な条件における水の構造解析・状態計測に応用可能である。今後、半導体製造現場の洗浄水、発電所の冷却水、環境中の流水など、さまざまなオンライン水計測への展開が期待される。
|
||||
|
2013
堀場雅夫賞
|
2013
堀場雅夫賞
|
慶応義塾大学 理工学部化学科
特任助教
|
研究題目
ダイヤモンド電極を用いた選択的センシングを指向した電極設計
|
水計測
|
|
水計測
ダイヤモンドは本来電気を通さない物質であるが、ホウ素を混ぜ込むことで導電性を示すようになる。この性質を利用するダイヤモンド電極は、白金や金を使用する従来型の電極に比べ、より多くの物質を高感度測定できる次世代の電極材料として幅広い応用が期待されている。一方で、従来電極と同様、溶液中の検出対象物質への選択性が課題とされ、測定を妨害する成分を事前に除去する必要がある。渡辺氏は、ダイヤモンド電極に金属を埋め込む独自手法を採用することにより、電極近傍での反応物の拡散を制御し、検出対象物質に対する選択性を向上させることに成功した。この研究は、環境中の重金属の測定などへの応用が期待され、前処理不要の高感度計測を実現する携帯型測定器実用化への貢献が見込まれる。
|
||||
|
2013
堀場雅夫賞
|
2013
堀場雅夫賞
|
米国 ウェインステート大学 化学科
助教
|
研究題目
高速サイクリックボルタンメトリーによる環境水中の微量金属の連続計測
|
水計測
|
|
水計測
環境水に汚染物質として含まれる微量金属については、健康被害防止や環境保全の観点から、現地での連続モニタリングが重要とされている。その手法として電極を用いた電気化学法が有望視されてきたが、計測時間や安定性といった性能が必ずしも十分ではなく、電極に使用される水銀の有害性も問題視されている。ハシェミ氏は、カーボン電極を用いて計測時間の短縮と水銀フリーを実現した“微量金属高速サイクリックボルタンメトリー”を開発し、微量の銅や鉛を0.1秒オーダーでリアルタイムに分析できることを示した。本技術は、ヒ素やクロムなど、他の微量金属の分析への応用も可能である。水資源の保全・監視および造水・浄化・再利用をする上で必要な情報源となる、環境水中の微量金属のリアルタイム計測技術として応用が期待される。
|
||||
|
2013
特別賞
|
2013
特別賞
|
埼玉大学大学院 理工学研究科
准教授
|
研究題目
新規蛍光プローブによる放射性廃棄体中および環境微生物中の重金属イオンの超高感度電気泳動法の開発
|
水計測
|
|
水計測
電気泳動法は、溶液に高い電圧をかけたときに、試料に含まれる物質の移動速度がそれぞれ異なることを応用する分離法である。対象成分の蛍光や光吸収を検知する検出器と組み合わせ、分離分析に広く利用される。しかし、水環境中の重金属イオン分析に対しては、十分な感度を示す検出方法がなく、適用が難しいとされてきた。齋藤氏は、目的の重金属イオンと結合し、安定して蛍光を発する物質(蛍光プローブ)を新規に設計するとともに、このような重金属イオンの選択的検出を実現する新しい電気泳動法を考案した。これにより、有害物質である鉛やアクチノイド※などの濃度を、pptレベルの高感度で、かつ少量のサンプルから測定できる分析手法を確立した。この技術は、放射性物質を含む廃水など、水溶液サンプル中の重金属イオン測定への応用が期待される。※アクチノイド:原子番号89~103にあたる元素の総称で、放射性のウランやプルトニウムもこのグループに含まれる。
|
||||
|
2012
堀場雅夫賞
|
2012
堀場雅夫賞
|
独立行政法人 放射線医学総合研究所
チームリーダー
|
研究題目
がん診断と放射線治療を融合する開放型PETイメージング手法および装置の開発
|
放射能計測
|
|
放射能計測
陽電子断層撮像法(PET)はがんの診断、放射線治療はその治療に広く用いられているが、それぞれは独立した技術である。山谷氏はこれら2つの技術の融合をめざし、PETによるイメージングと同時に放射線治療も行なえるよう、患者を覆う面積を少なくした新しいPET装置「OpenPET」のコンセプトを提案した。さらに、新たに開発した3次元放射線位置検出器を用いることで、治療ビームを通すのに十分な隙間のある装置を実現した。あわせて、放射線治療との融合に必要な画像処理技術も検証している。OpenPETは、「PETでがんの様子を観察しながらの放射線治療」など、より効果的な将来の放射線治療への貢献が期待できる。*PET:Positronemissiontomography(陽電子断層撮像法)。画像診断装置の一種。陽電子を放出するごく微量の放射性物質を体内に取り込み、そこからの放射線(陽電子)の分布を検出して、コンピュータ処理で画像化(イメージング)する技術。
|
||||
|
2012
堀場雅夫賞
|
2012
堀場雅夫賞
|
名古屋大学大学院 理学研究科
助教
|
研究題目
超高速原子核乾板自動飛跡読取装置の開発とその応用
|
放射能計測
|
|
放射能計測
「原子核乾板」は、感光現象を利用して、放射線が通過した跡(飛跡)をサブマイクロ(1万分の1ミリ)単位で記録できる。中野氏は、この原子核乾板に記録された飛跡を機械的かつ自動で読み取る装置の実用化に、世界で初めて成功した。以来、装置構造や画像処理技術の改良により、読み取り速度の高速化を進めている。読み取り速度は、現在までに開発当初と比べて約1万倍と飛躍的に向上し、「世界最高速」を実現している。この装置はニュートリノの研究など多くの分野に貢献しており、将来的には、原子核乾板をもちいた火山や原子炉など大型構造物の調査研究への応用も期待される。
|
||||
|
2012
堀場雅夫賞
|
2012
堀場雅夫賞
|
東北大学大学院 工学研究科 応用化学専攻
准教授
|
研究題目
ナノ構造を有するシンチレータ材料の開発
|
放射能計測
|
|
放射能計測
放射線があたると発光する蛍光物質はシンチレータと呼ばれ、その感度の高さや応答の速さにより、基礎科学研究から環境モニタリングに至る幅広い分野で放射線検出器として使用されている。その一方、シンチレータとして利用されてきた既存の材料には、現状以上の応答高速化が困難という問題点があった。越水氏は、シンチレータ材料開発に際して、ナノメートルスケールの微細な構造(ナノ構造)を構築するという手法を確立し、より高速な応答を示すシンチレータ材料を開発した。ナノ構造の導入によってシンチレータ設計の自由度が格段にあがり、より広い用途に応用できる高性能のシンチレータ開発へつながることが期待される。
|
||||
|
2012
特別賞
|
2012
特別賞
|
オークリッジ国立研究所 物理部門
研究員
|
研究題目
エキゾチック原子核の構造解析用検出器(オークリッジ・ラトガース式円筒型検出器)の開発
|
放射能計測
|
|
放射能計測
通常に比べて中性子の数が極端に多い「エキゾチック原子核(不安定原子核)」は、一般的な安定原子核の生成に大きく関わっている。しかしながら、エキゾチック原子核は非常に寿命が短いため、その構造や性質を調べることが難しい。オークリッジ国立研究所とラトガース大学のグループは、エキゾチック原子核を加速器内で生成し、瞬時に重水素に衝突させるという手法で、その研究を行っている。この手法でエキゾチック原子核に関する情報を得るには、衝突で飛び出す陽子のエネルギーや方向を高精度で特定することが重要である。ペイン氏は、プロジェクトに不可欠な検出器として、陽子を広い立体角で捕捉できる円筒型検出器を開発した。エキゾチック原子核の研究は、超新星爆発や中性子星の合体など、宇宙で起こる元素生成プロセスの解明に貢献すると期待されている。
|
||||
|
2011
堀場雅夫賞
|
2011
堀場雅夫賞
|
独立行政法人 理化学研究所
専任研究員
|
研究題目
新しい高感度非線形レーザー分光法の開発と界面分子構造研究への応用
|
電磁波
|
|
電磁波
山口氏は、超短パルスレーザー技術を駆使して、界面*1だけを選択的に、かつ高感度に観察できる非線形レーザー分光法を開発した。開発した手法により、従来ではまったく考えられなかったような質や情報をもつ界面電子スペクトルの取得に世界で初めて成功した。この測定法により、界面分子の電子状態、振動状態、およびその時間的変化を、自由自在に評価できるようになった。今後、本手法は、電池内や細胞表面で起こる化学反応の理解など、様々な界面科学分野に応用されることが期待される。*1界面:水と油のように異なる物質が混ざらず、かつ触れ合って存在している場合、両者の境界を界面と呼ぶ。厚さにして100万分の1ミリ程度という界面での化学反応の理解は、生命現象の解明や、種々の材料開発に重要なものとなっている。これまでは、その界面だけを選択的に測定する有効な手法は確立されていなかった。
|
||||
|
2011
堀場雅夫賞
|
2011
堀場雅夫賞
|
独立行政法人 産業技術総合研究所
主任研究員
|
研究題目
表面増強ラマン散乱の電磁増強機構の実証と生細胞表面タンパク質の単分子リアルタイム検出への応用
|
電磁波
|
|
電磁波
伊藤氏は、表面増強ラマン散乱(SERS*1)の発現機構を解明するとともに、SERSを利用した新しい単一ナノ粒子凝集体顕微分光法を開発した。さらに、SERSの分子識別能の高さを活かし、表面タンパク質1分子*2のリアルタイム検出に初めて成功した。この方法により大腸菌・ピロリ菌などを特徴づける表面タンパク質分子を検出することで、従来数日かかっていた培養などの手間をかけずに、それらの細菌の有無をリアルタイム検出できる可能性がある。さらに、この研究は、その他の生体組織の高感度検出法や、生細胞中の生体関連物質分子のリアルタイム分析手法への応用も期待できる。*1SERS:銀などの金属ナノ粒子が介在することにより、本来微弱なラマン散乱光が劇的に増幅される現象。非常に高感度のラマンスペクトルが得られ、スペクトルに基づく物質の定性に有用な手法として知られる。しかし、本研究までは、この現象の詳細な原理は明らかにされていなかった。*2表面タンパク質分子:生体組織や細菌の細胞表面に存在するタンパク質分子は、細胞内外の物質輸送など非常に重要な機能を担っている。表面タンパク質分子は組織や細菌ごとに異なっており、それを識別することで細胞を特定できる可能性がある。
|
||||
|
2011
堀場雅夫賞
|
2011
堀場雅夫賞
|
名古屋大学大学院 工学研究科
准教授
|
研究題目
レーザー分光法とマイクロデバイスを組み合わせた超高感度迅速分析法の研究
|
電磁波
|
|
電磁波
渡慶次氏は、レーザー分光法(熱レンズ法や蛍光法)とマイクロデバイス技術とを組み合せることで、微量の生体由来物質を超高感度に迅速分析する技術を開発した。非蛍光性分子の単分子レベルの定量に世界で初めて成功したほか、熱レンズと蛍光検出のハイブリッド化や全自動小型免疫分析装置の実現など、革新的な検査技術確立のための研究・開発を行った。本研究により、従来の約100分の1の血液量での免疫分析が可能となり、患者の採血時の負荷を画期的に減らす可能性が示された。採血したその場での診断など、テーラーメイド医療*1をはじめとする今後の医療・ライフサイエンス分野での貢献が期待される。*1テーラーメイド医療:患者一人一人の体質(遺伝子の差異)に応じた医療。
|
||||
|
2011
特別賞
|
2011
特別賞
|
フランス国立科学研究センター
研究員
|
研究題目
細胞を用いたラベルフリーバイオセンサー及びバイオチップ -医療診断や食品安全性評価への切り札となり得るか?-
|
電磁波
|
|
電磁波
Roupioz氏は、電気化学的手法によってチップ上に抗体アレイ*1を形成し、表面プラズモン共鳴イメージング*2によって血中細胞や細菌を無標識で検出する手法を開発した。さらに、微細加工技術で形成したマイクロペンシルを用いて直径5~10μm程度の微小範囲に抗体をアレイ化する技術を開発し、超小型チップによる細胞の検出を実現した。現在は、この技術を応用し、さまざまな細胞をリアルタイムで識別する技術などを開発中である。医療・食品・環境分野において重要な次世代の細胞検出技術として、今後の進展が期待される。*1抗体アレイ:チップ上で抗体を配列させて固定化したもの。*2表面プラズモン共鳴イメージング:金属箔膜上に固定した分子に他の分子が結合した場合に、薄膜を通して当てた光の屈折率が変わる現象(表面プラズモン共鳴)を用いた、試料状態の画像化技術。
|
||||
|
2010
堀場雅夫賞
|
2010
堀場雅夫賞
|
財団法人 レーザー技術総合研究所
研究員
|
研究題目
高強度フェムト秒レーザーを用いた白色光ライダーの開発
|
内燃機関
|
|
内燃機関
高強度フェムト秒レーザーを希ガスに集光する事で得られる紫外から赤外領域に及ぶ超広帯域スペクトルを有するコヒーレント白色光を用いて、大気環境を計測する白色光ライダーを開発した。この技術は、散乱の波長依存性を利用した大気中エアロゾルの粒径分布の推定、偏光特性を利用した黄砂の識別、赤外域を利用した二酸化炭素の濃度計測などの広域かつ多種多様な環境計測に応用できる。白色レーザー光源のコンパクト化にも取り組み、実現性が高い計測技術として期待される。
|
||||
|
2010
堀場雅夫賞
|
2010
堀場雅夫賞
|
米国 プリンストン大学
助教
|
研究題目
レーザー分散効果を応用した大気中の反応性化学種の高感度その場計測技術
|
内燃機関
|
|
内燃機関
試料大気に磁場をかけ、量子カスケードレーザー(QCL)を用いて常磁性の分子をファラデー回転分光で検出するという、斬新かつ画期的な技術を開発した。この手法によりバックグラウンドシグナルを低減させ、一酸化窒素(NO)0.38ppbの検出感度を持つ技術の確立に至った。この技術を応用して小型化したワイヤレス微量ガスセンサを用いて、広い地域をカバーする観測ネットワークの試験を実施している。高感度のガス分析計の基礎技術の応用だけでなく、広域モニタリングに発展する可能性が期待される。
|
||||
|
2010
堀場雅夫賞
|
2010
堀場雅夫賞
|
首都大学東京 都市環境科学研究科
教授
|
研究題目
ポンプ・プローブ法によるOH反応性測定と大気質診断法の開発
|
内燃機関
|
|
内燃機関
反応性大気成分ガスの網羅的な観測を行う代わりに、OHラジカル反応性を測定することで同様の情報を引き出す、新しい方法を提案した。大気中のOHラジカルはほとんどの化学物質と高い反応性を示すため、大気中での直接的な検出と測定は困難である。本研究では、紫外線パルスレーザーを試料大気に照射してOHラジカルを生成させ、その減衰挙動をレーザー分光で観測することで、反応性物質の総量に相当する情報を得ることができるシステムを構築した。東京郊外で本手法による大気観測を実施し、同時に100種類もの化学成分ガスを測定し、それぞれの測定値を比較した結果、25~50%もの未知なるOH反応性物質の存在が確認され、大気のオキシダント生成能を評価する新しい概念を提案した。
|
||||
|
2009
堀場雅夫賞
|
2009
堀場雅夫賞
|
スペイン オビエド大学
准教授
|
研究題目
半導体表面の無機/有機物計測のための新しいソフトイオン化技術を用いた大気圧グロー放電飛行時間質量分析計の開発および評価
|
半導体
|
|
半導体
固体表面の前処理なしでかつ、大気圧グロー放電を利用してサンプルにダメージを与えないソフトイオン化技術を採用した飛行時間質量分析計を開発した。本分析計のシリコン表面における質量分析の検出限界は非破壊計測でありながら~10ng/gに到達しており、破壊法で高感度の二次イオン質量分析計に迫るレベルである。単結晶、あるいは多結晶シリコンなどの表面の非破壊質量分析を高速・高感度で行うことが可能であることから、今後この分析計が半導体デバイス、さらには太陽電池の製造工程における非破壊コンタミネーション計測に大きく貢献することが期待される。
|
||||
|
2009
堀場雅夫賞
|
2009
堀場雅夫賞
|
独立行政法人 物質・材料研究機構
グループリーダー
|
研究題目
蛍光X線分光法による超微量分析 -新しい高効率波長分散型X線分光器の開発と高輝度シンクロトロン放射光による全反射蛍光X線分光法への応用-
|
半導体
|
|
半導体
高輝度放射光(SPring-8)と独自の工夫を導入した超小型・超高効率のX線分光器の技術を組み合わせた新しい全反射蛍光X線分光法の開発により、従来報告されていた最良の検出限界を一桁以上も更新する10-16gレベルの世界一の高感度化を達成した。この研究では、光源の高性能化に見合った分光技術と分光器の開発が超微量分析のブレークスルーをもたらした。単なる元素分析にとどまらず、分光器の高分解能性を生かして微量物質の化学状態分析も可能になった。さらに将来は、短パルスX線による化学変化・反応の研究への発展も期待されている。
|
||||
|
2009
堀場雅夫賞
|
2009
堀場雅夫賞
|
横浜国立大学大学院 工学研究院
特別研究教員
|
研究題目
表面差分反射分光と反射率差分光によるSi表面上のO2, NO, CO 反応の研究
|
半導体
|
|
半導体
半導体デバイス作製上重要なSiO2の膜形成に関して、可視-近紫外光を用いた表面差分反射分光(SDR)と反射率差分法(RDS)が単原子層での観測感度を有することを実証し、また、SiO2/Si界面に形成されるひずみを定量化できる可能性を見出した。これら手法は、シリコンウェハ表面における薄膜成長過程などをその場観察することが可能であり、高感度な原子レベルの解析やプロセス制御技術への展開が期待される。
|
||||
|
2009
特別賞
|
2009
特別賞
|
京都大学大学院 工学研究科 材料工学専攻
日本学術振興会特別研究員
|
研究題目
超高感度小型全反射蛍光X線分析装置の開発
|
半導体
|
|
半導体
全反射蛍光X線分光法では単色X線を用いた方が高感度であるという常識を覆し、数WのX線管を用いた多色X線の場合では放射光を用いた全反射X線分光法に迫る高感度化と小型化が可能であることを見出し、この結果を基にハンディー全反射蛍光X線分光装置を開発した。本装置は、半導体プロセスのインライン分析装置としての可能性を有しており、この分野への展開に向けてさらなる技術開発が期待される。
|
||||
|
2008
堀場雅夫賞
|
2008
堀場雅夫賞
|
明治大学 理工学部 機械情報工学科
専任講師
|
研究題目
ディーゼル噴霧火炎内すす生成過程のレーザー計測
|
ガス計測
|
|
ガス計測
レーザ誘起蛍光(LIF)法およびレーザ誘起赤熱(LII)法を用いてディーゼル噴霧火炎中のすす前駆物質とすす粒子の同時2次元可視化をおこない、すすの生成領域・時期を特定した。さらに、多波長レーザを光源とする励起発光マトリクス(EEM)法を新たに開発し、これを噴霧火炎に適用した。これにより、燃焼の進行に伴って多環芳香族炭化水素(PAH)の多環化、すす粒子への転化がおきることが明らかになった。本計測法により得られる知見は、すす排出予測モデル構築の基礎として重要であり、低エミッションエンジンシステムの実現に大きく貢献することが期待される。
|
||||
|
2008
堀場雅夫賞
|
2008
堀場雅夫賞
|
アルバータ大学 機械工学科
准教授
|
研究題目
内燃機関から排出されるナノ粒子の質量分析装置の開発
|
ガス計測
|
|
ガス計測
エンジンから排出されるナノ粒子の質量分布を計測できる、クエット遠心粒子質量分析(CouetteCPMA)法を開発した。この方法は、従来のエアロゾル粒子質量分析(APM)法にクエット流れを導入する改良を加え、粒子ロスの低減を実現したものである。CouetteCPMAで得られる質量データを微分型電気移動度分析法(DMA)などで得られる粒子径データと組み合わせることで、粒子の有効密度とフラクタル次元を求めることができる。ナノ粒子の排出質量計測手法として非常に有用であり、ナノ粒子の健康影響評価や後処理装置の開発などに大きく貢献する可能性がある。
|
||||
|
2008
堀場雅夫賞
|
2008
堀場雅夫賞
|
米国 ウィスコンシン州 ウィスコンシン大学マディソン校
准教授
|
研究題目
HCCI 燃焼における残留ガスおよび温度の同時可視化
|
ガス計測
|
|
ガス計測
2波長のレーザを用いた平面レーザ励起蛍光(PLIF)法を予混合圧縮着火(HCCI)エンジンに適用し、エンジン筒内の残留ガスと温度の分布を連続的に計測する技術を確立した。この技術によれば、筒内の排気再循環(EGR)の状態や温度の変化を、吸気から圧縮・膨張工程にわたって2次元画像として可視化でき、バルブ動作のタイミングなどのパラメータによる影響の解析も可能である。高効率と低エミッションを両立しうる次世代エンジンとして注目されるHCCIの研究に対して、実用化に向けた燃焼解析手法を提供できる技術として期待される。
|
||||
|
2008
特別賞
|
2008
特別賞
|
岡山大学大学院 自然科学研究科
准教授
|
研究題目
点火プラグ実装型燃料・残留ガス濃度計測センサシステムの開発
|
ガス計測
|
|
ガス計測
光ファイバ・サファイアレンズ・金属ミラーを組み合わせ、エンジン点火プラグ近傍の燃料濃度・CO2濃度を計測できる点火プラグ埋め込み型赤外センサシステムを開発した。このセンサシステムをロータリーエンジン、高過給ディーゼルエンジンなどの実用機関に適用し、点火プラグ近傍の燃料・空気の混合気形成過程、点火時期での燃料濃度と初期燃焼期間などを明らかにした。本手法では、エンジンを改造することなく、燃焼に大きく影響するプラグ近傍の燃料濃度・CO2濃度を計測できる。エンジンの熱効率を飛躍的に向上させるための研究開発への応用が期待される。
|
||||
|
2007
堀場雅夫賞
|
2007
堀場雅夫賞
|
京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科
准教授
|
研究題目
並列ディジタルホログラフィック顕微鏡法による細胞の3次元動画像計測法およびその装置の開発
|
生体粒子
|
|
生体粒子
細胞や生体粒子の瞬時3次元画像計測を実現するために、並列位相シフトディジタルホログラフィを発明し,その原理を実証した。この技術は、面内に異なる位相を持つ光波を用いて、一瞬に形成される干渉縞画像を撮影して、任意の奥行き位置での焦点の合った画像を画像処理で再生するものである。この技術により、高速で動く被写体の3次元動画像計測を実現できるようになった。また、本技術に複数の波長のレーザ光を用いることにより、瞬時3次元カラー画像計測の有効性も確認した。この技術に基づくシステムは医薬・診断方法や食品検査など産業応用への大きな貢献が期待される。
|
||||
|
2007
堀場雅夫賞
|
2007
堀場雅夫賞
|
独立行政法人 海洋研究開発機構 極限環境生物圏研究センター
グループリーダー
|
研究題目
圧力で探る生体膜と膜タンパク質のダイナミクス研究
|
生体粒子
|
|
生体粒子
数百気圧もの高圧力は細胞にどのような影響を及ぼすのかについて、酵母菌をモデルに「圧力生理学」という新たな着想から研究を行った。その結果、生命維持において重要なトリプトファン輸送の特殊性を、圧力研究の観点から世界で初めて体系化した。また、生化学と物理計測の融合を図り、細胞膜上に存在するアミノ酸輸送体の動態を体積変化として定量することに初めて成功した。さらに生体膜構造については蛍光異方性プローブを用いた蛍光寿命測定を実施し、ナノ秒レンジのダイナミックな動きをとらえた。今後、顕微鏡下で蛍光寿命測定を実現する新システムを実現することで、医学・基礎生物学への貢献が大いに期待される。
|
||||
|
2007
堀場雅夫賞
|
2007
堀場雅夫賞
|
米国カンザス州立大学
化学科 助教授
|
研究題目
微細流路デバイスにおけるT-リンパ細胞の迅速分析
|
生体粒子
|
|
生体粒子
微小流路デバイスを利用することにより、T-リンパ球の培養、1細胞の操作、細胞溶解、内容物の分離分析のすべてが行えるデバイスを実現した。このデバイスは複数の微細流路を機能的にデザインしたチップであり、微細化の効果により従来の技術に対して分離の高効率化、強電場の利用が可能である。本研究のアプリケーションとして細胞中の酵素活性のモニターと酵素活性化の研究を目指している。また、将来的には生体細胞と病気との関連に分析することにより、癌などの病気の初期段階を検査できる可能性がある。
|
||||
|
2006
堀場雅夫賞
|
2006
堀場雅夫賞
|
財団法人 高輝度光科学研究センター
主幹研究員
|
研究題目
高エネルギー放射光を用いたマイクロビーム蛍光X線分析法の革新とその応用
|
X線
|
|
X線
大型放射光施設(SPring-8)で得られる高エネルギーX線領域での集光光学素子の開発を行ない、1マイクロメートルの微小ビームの形成に成功した。その応用により、カドミウムを蓄積する植物において各組織内の元素分布が明らかになるなど、蛍光X線による微量重金属元素の分析が可能であることを実証した。また、高エネルギー放射光蛍光X線分析の手法を開発することで、希土類元素などの微量重元素の非破壊高感度分析を可能とし、和歌山ヒ素カレー事件の亜ヒ酸鑑定など、鑑識・環境・文化財などの各分野において具体的成果をあげた。
|
||||
|
2006
堀場雅夫賞
|
2006
堀場雅夫賞
|
日本女子大学 理学部 物質生物化学科
助教授
|
研究題目
共鳴X線非弾性散乱を利用した新しいX線分光法の開発
|
X線
|
|
X線
共鳴X線非弾性散乱の高精度測定を通じて、内殻寿命幅による分解能制限なしに、X線吸収微細構造(XAFS)スペクトルを求める方法を開発した先駆的研究。最近では、世界最高感度の微弱発光分光システムを独自に作り上げ、それを放射光施設SPring-8に持ち込み、「寿命幅制限のない価数選別XAFS」や「寿命幅制限のないスピン選別XAFS」測定など、従来のXAFS分光法では不可能だったことを次々と実現させている。本測定・解析法は、高温超電導材料や磁性材料、機能性材料全般について、様々な状態変化を追う極めて強力なツールに発展する可能性がある。
|
||||
|
2006
堀場雅夫賞
|
2006
堀場雅夫賞
|
アントワープ大学 分析化学科
教授
|
研究題目
種々の環境試料や文化遺産試料における主成分並びに微量成分のX線による化学種の同定
|
X線
|
|
X線
X線管及び放射光を光源とする微細X線ビームを用いた分析装置並びに分析方法の開発を行なった。それにより、ローマから中世のガラスなどの微小な文化遺産や、放射能汚染された地域の微粒子などの環境試料の分析に成果をあげた。また、相補の関係にある蛍光X線分析法とラマン分光法とを組み合わせた共焦点式ポータブルラマンX線装置を開発し、試料表面の化学種の情報が得られるようになり、犯罪捜査の物的証拠や土壌などの環境試料、文化遺産などの現場における物質の同定に非常に有用であることを実証した。
|
||||
|
2006
特別賞
|
2006
特別賞
|
東京理科大学
教授
|
研究題目
乳がんの早期診断をめざすシステム開発
|
X線
|
|
X線
放射光を用いて生体軟組織のX線屈折コントラスト像を得るX線暗視野法を応用し、乳がんなどの早期診断システムの開発を行っている。X線暗視野法は、シリコン単結晶の非対称反射と患部の後方に置かれたシリコンの角度分析板により、患部で屈折を起こしたX線のみを取り出すもので、がん組織と正常組織の僅かな屈折率の違いを高いコントラストで描画できる。また、屈折像からCT像を得るアルゴリズムを開発し、非浸潤性乳管がんの3次元像の病理診断スライス像との非常に良い一致が見られた。
|
||||
|
2005
堀場雅夫賞
|
2005
堀場雅夫賞
|
関西学院大学 理工学部
博士研究員
|
研究題目
赤外分光法とX線回折法による生分解性高分子のC-H・・O水素結合の研究-”弱い水素結合”が結晶構造安定化と熱的挙動に果たす役割-
|
赤外線
|
|
赤外線
生分解性高分子であるポリヒドロキシブタン酸(PHB)の結晶構造や熱挙動を赤外分光法とX線回折法を併せ用いて研究した。その結果、PHBの結晶構造中にC-H…O=C相互作用が存在することを世界で初めて見出した。このC-H…O=C水素結合が結晶構造の安定化や共重合体の高結晶化度への重要な役割を果たしていることを明らかとし、PHB結晶構造のモデルを提案した。
|
||||
|
2005
堀場雅夫賞
|
2005
堀場雅夫賞
|
日本大学 生産工学部 応用分子化学科
助教授
|
研究題目
多角入射分解分光法:仮想光概念を利用した計測法の構築
|
赤外線
|
|
赤外線
物質間の界面の特異的な分子層や界面吸着種を赤外分光法で分子配向解析を確立した研究である。特に赤外多角入射分解分光(赤外MAIRS)法は光学の常識を一新する、まったく新しいコンセプトである。赤外MAIRS法の新規開発・解析手法の構築は、ソフトマテリアル(LB膜や有機EL膜など)材料の構造解析に非常に役立つことが期待できる。
|
||||
|
2005
堀場雅夫賞
|
2005
堀場雅夫賞
|
大阪大学大学院 生命機能研究科
助教授
|
研究題目
近接場ナノ振動分光学の開拓研究
|
赤外線
|
|
赤外線
赤外ラマン分光法に近接場光学技術を導入した先駆的な研究である。とくに、波長可変の高輝度赤外レーザーと先端に微小開口を有する原子間力顕微鏡用カンチレバーを用いた赤外近接場顕微鏡、および、金属ナノ探針を用いた近接場ナノラマン顕微鏡の考案、試作の結果は、波長よりも微小な領域の顕微観察・分析を可能とし、さらに新たなラマン効果の現象の発見につながった。この方法を利用することで分子種の特定だけではなく、分子の配向方向も決定できることが期待できる。
|
||||
|
2005
特別賞
|
2005
特別賞
|
ノッティンガム大学 化学科
教授
|
研究題目
Development of infrared spectroscopy analyzer with high time resolution (picosecond) peformance.
|
赤外線
|
|
赤外線
|
||||
|
2004
堀場雅夫賞
|
2004
堀場雅夫賞
|
東北大学大学院 環境科学研究科 環境科学専攻
助手
|
研究題目
電位差法による超臨界水溶液のpH測定装置の開発
|
pH
|
|
pH
超臨界水溶液のpHを直接かつ高精度で評価可能な装置を世界で初めて開発。超臨界水反応場を利用したナノ粒子やナノワイヤーといった新規機能性金属酸化物材料の設計や、廃棄バイオマスからの有用化学原料の回収プロセスの構築に寄与するものと期待される。
|
||||
|
2004
堀場雅夫賞
|
2004
堀場雅夫賞
|
甲南大学 先端生命工学研究所(FIBER) 所長 / 理工学部機能分子化学科
教授
|
研究題目
DNAをセンシング素材として用いた細胞内pH測定法の開発
|
pH
|
|
pH
DNA(デオキシリボ核酸)を検出媒体とした世界でも類のない、細胞内のpHを測定できるpHセンサーを開発。生体分子をセンサーの素材として活用する試みは、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーの分野で注目を集めており、本pHセンサーは、簡便に細胞内のpH測定ができるため、癌の早期診断やアポトーシス(細胞死)検出のための新しい診断システム開発に発展すると期待される。
|
||||
|
2004
堀場雅夫賞
|
2004
堀場雅夫賞
|
財団法人 電力中央研究所 環境科学研究所 陸・水環境領域
主任研究員
|
研究題目
ISFET-pH電極を用いた海洋の現場計測用pHセンサの開発
|
pH
|
|
pH
海洋の表層から深海までの海水のpHを高精度に現場で計測できるpHセンサを開発し、実際の海洋において現場pH計測を行ってきた。pH電極にイオン感応性電界効果型トランジスター(ISFET)を用いることで、水溶液中での高精度かつ長時間連続観測が可能になった。地球規模の炭素循環に対して、海洋の果たす役割やメカニズムの解明に役立てることで、地球環境の将来予測も可能になると期待される。
|
||||